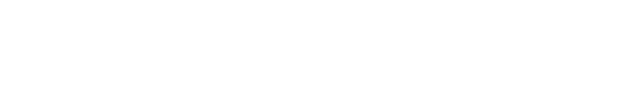肝機能障害
肝機能障害とは?
肝臓の機能障害を認める状態のことをいいます
会社などの健康診断で指摘されることが多く、その際は採血結果のAST・ALT・γーGTPなどの項目で異常値を認めます。
肝機能障害を起こす原因は?
- 脂肪肝
- アルコール性肝障害
- ウイルス性肝障害(B型肝炎・C型肝炎)
- 胆道系の疾患によるもの(胆石症・胆管がんなど)
- 自己免疫性肝炎
- 薬物性
脂肪肝
摂取しすぎた脂肪が肝臓内へ蓄積され続けることにより肝機能障害へ進行している状態を脂肪肝といいます。
ほとんど自覚症状はなく、静かに進行していきます。
原因は肥満・飲酒などの生活習慣によるものがほとんどです。
脂肪肝が進行すると肝炎へ発展し、さらに無治療のまま進行することで肝硬変へと発展します。いったん肝硬変になってしまうといくら治療しても元の正常の肝臓へは戻ることはありません。肝硬変は肝細胞がんの原因となることがあるため、肝硬変へ進行する前に脂肪肝を治療することが重要です。
アルコール性肝障害
長期間のアルコール過剰摂取により引き起こされる肝機能の障害です。アルコールの肝臓による代謝の際に細胞障害が起こるとされています。またアルコールの過剰摂取の際に多量に産生される中性脂肪が肝臓内に蓄積され、アルコール性脂肪肝を発症します。
アルコール性肝障害のほとんどの方はアルコール性脂肪肝から始まります。
アルコール性脂肪肝→アルコール性肝炎→アルコール性肝硬変へと順を辿り進行していきます。
アルコール性肝障害の症状
初期の段階では目立った自覚症状はありません。
全身倦怠感・食欲低下・嘔気・肝腫大などが出現した場合は肝炎へ発展している可能性があり要注意です。
さらに症状が進行すると肝硬変となり、黄疸・浮腫・腹水貯留を認めるようになります。末期状態になると吐血・意識障害・出血傾向を伴うようになります。
*過剰飲酒とは、1日に純エタノールに換算して60g以上の飲酒をいいます。しかし女性やお酒に弱い人では、1日40g程度の飲酒でもアルコール性肝障害が起こる可能性があると言われています。
ウイルス性肝炎
肝炎ウイルスに感染し、肝臓に炎症が起こる疾患です。
肝炎ウイルスにはA型からE型まで5種類が存在しますが、国内で多く見られるのはB型とC型です。
B型肝炎ウイルスとC型肝炎ウイルスの主な感染経路は過去の輸血・注射針の共有・性行為・母子感染です。輸血や注射針の共有による肝炎の感染は現在では見られなくなっているため、性行為による感染が現在の主な感染経路となっており、精液や唾液、膣分泌液により感染します。
ウイルス性肝炎の症状は?
初期症状として倦怠感・食欲低下などが持続した後に腹痛や嘔吐などの消化器症状と黄疸(身体が黄色くなる)が出現します。
B型・C型肝炎に持続感染してもほとんどの場合は自覚症状がないまま経過します。しかし、放置しておくと慢性的に肝臓に炎症を起こし、肝硬変や肝臓がんへ進行していきます。
肝硬変とは?
ウイルス性肝炎・アルコール性肝障害などで長期間肝臓にダメージを受けることで肝臓の組織が固くなり、機能が低下している状態のことです。
肝硬変の症状
- 腹水:血液中から漏出した体液が腹腔内にたまることで起こります
- 黄疸:ビリルビンという物質が体内に多くなることで皮膚や眼が黄色くなります。
- 浮腫:肝臓の栄養素の代謝や吸収が悪くなり、手や足がむくんできます
- 食道静脈瘤:肝臓への血流が滞ることで食道や胃の静脈に瘤ができます。進行すると大出血を起こします。
- 肝性脳症:肝臓の機能低下によりアンモニアの代謝が悪くなることで意識障害を起こします。
- 肝臓がん:硬くなった肝臓からがんが発生しやすくなります。
自己免疫性肝炎
免疫システムが異常に働き、リンパ球が幹細胞を攻撃することで肝機能障害を起こします。
中年の女性に多く発症する傾向にあります。
遺伝的な要因・ウイルス感染・薬物・妊娠出産などがきっかけとなることがありますが、原因は不明です。
治療を行わなければ進行は早く、肝硬変や肝不全へ移行する場合がありますが、適切な治療を行うことで進行を止めることが出来ます。